癒しが足りないと、心は「戦い続ける」状態になる
休んでいるのに、疲れが取れないのはなぜ?
あなたには「好きなもの」や「ほっとする時間」はありますか?
例えば、
- お気に入りのカフェで静かに本を読む時間
- 心を許せる人と笑い合うひととき
- 動物と過ごす
- 穏やかで何も考えなくていい瞬間
そんなとき、体の力がふっと抜けて、呼吸がゆっくりになる。これが本来の“癒し”です。
けれど、忙しさや責任に追われる毎日の中で、私たちはいつのまにか「癒されること」を後回しにしてしまいます。すると脳はずっと「緊張モード(交感神経優位)」のままになり、眠っても疲れが取れない、集中できない、心が硬くなる──やがて“何をしても満たされない”状態に陥ってしまいます。
癒しを取り入れないことは、脳と体の「安全スイッチ」を切ったまま生きている状態なのです。癒しは贅沢でも甘えでもありません。むしろ、心と体を再起動させるために欠かせない“生命のメンテナンス”です。
「癒し」とは何か:脳が安全を思い出すプロセス

副交感神経と安心ホルモン
脳科学的に見ると、「癒し」は副交感神経を優位にする行為です。副交感神経が働くと、心拍数がゆるみ、呼吸が深くなり、血流が全身に行き渡ります。
このとき、脳内では次のようなホルモンが関与します:
- オキシトシン:安心や信頼に関与するホルモン。人とのつながりで増えます。
- セロトニン:感情の安定に寄与します。
- ドーパミン:満足感や意欲に関係します。
脳が「安全だ」と判断した瞬間、思考のノイズが減り、感情が整い、「本当にやりたいこと」や「好きなもの」にアクセスしやすくなります。つまり、癒しは単なる気持ちよさではなく、自分らしく生きるための前提条件です。
なぜリラックスできない人が多いのか

現代において癒しを取り入れにくい背景には、主に思考・習慣・社会の3つの要因があります。
思考のクセ:「頑張らなければ価値がない」
「努力=正義」「休むのは怠け」といった価値観が根付くと、休むことに罪悪感が生まれます。脳は常にタスクモードになり、リラックスする余地を失います。
習慣の問題:「思考が止まらない日常」
スマホ通知やSNS、情報の洪水で脳は1日中フル稼働。夜になっても思考が続き、眠っても疲れが取れない…という状態に陥りやすくなります。
社会的要因:「安心より成果を重視する文化」
学校や職場で効率や成果が優先されると、「安心して立ち止まっていい」というメッセージが届きにくくなります。結果として、癒しを求めること自体が後回しにされます。
癒しを取り戻す3つのステップ

癒しは「特別な体験を足すこと」ではなく、「すでにある安心を思い出すこと」です。以下の3ステップを日常に取り入れてみてください。
ステップ①:「安心」を感じる時間を意識的につくる
脳が「安全だ」と感じた瞬間に癒しは始まります。1日5分でもいいので、次のような時間を設けてみましょう。
- 好きな場所・匂いで、好きな音楽を静かに聴く
- 動物や自然に触れる
- 心が落ち着く場所でぼーっとする
- お気に入りの入浴剤でゆっくり湯船につかる
ポイントは「何をするか」より「安心を感じられているか」です。
ステップ②:「考える」から「感じる」へシフトする
思考の過剰稼働を止めるには、まず心や体の感覚に意識を戻すこと。何かをすることではなく、今どういう感情が出ているのかを知るだけで、脳は落ち着きを取り戻します。
ステップ③:「安心」を習慣にする
癒しは一度きりの経験ではなく習慣です。小さな安心を毎日の習慣にすることで、脳は「ここは安全だ」と学習し、リラックスを取り戻しやすくなります。具体例:
- 寝る前の照明を柔らかくする
- SNSを見る時間を制限する
- 温かいお茶をゆっくり味わう
癒しは「生きる力」を取り戻すプロセス
癒されることは現実逃避でも甘えでもありません。それは、長く続く人生を生き抜くための回復の知恵です。脳が安心を思い出したとき、私たちは自然とやわらかくなり、他者にも自分にも優しくなれます。
今日から少しだけ、日常の中に「安心」を取り入れてみてください。それは、あなたが本来の力を取り戻すための、自然で科学的な一歩になります。


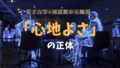
コメント