スマホを触るほどメンタルに悪い理由|脳科学と心理学から見た危険性と対策
朝起きてすぐスマホを手に取り、夜寝る直前まで画面を眺めていませんか?
体は元気なのに、なぜか気持ちが落ち込みやすい…そんな人が近年急増しています。
実はスマホの使いすぎは、脳や自律神経、感情面にまでじわじわと影響を与えているのです。
1. 情報過多による脳疲労

スマホは1分間に大量の情報を脳に送り込みます。
アメリカ・カリフォルニア大学の研究によれば、現代人が1日に受け取る情報量は、1980年代の約5倍にもなっています。
脳は処理しきれない情報にさらされ続けると、常に“軽いストレス状態”となり、集中力低下ややる気の減退、思考力の浅さを招きます。
2. SNSによる比較と承認欲求の刺激
SNSでは他人の“加工された良い部分”ばかりが目に入ります。
ペンシルベニア大学の研究では、SNS利用時間を1日30分以内に制限した学生は、うつ症状や孤独感が有意に減少しました。
自分の生活が他人より劣って見える「SNS疲れ」は、自己肯定感の低下と不安感の増加を引き起こします。
3. 睡眠の質低下

スマホのブルーライトは、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制します。
ハーバード大学の研究では、寝る前にブルーライトを浴びた被験者は、メラトニン分泌が約2時間遅れたことが確認されました。
睡眠が浅くなることで、翌日の感情コントロールが難しくなり、メンタルの安定を損ないます。
4. 姿勢と呼吸の悪化
スマホを長時間使うと首や肩が前に出る「スマホ首」になります。
胸が圧迫され、呼吸が浅くなり、自律神経が乱れやすくなります。
浅い呼吸は脳への酸素供給を減らし、気分の落ち込みや不安感を増大させることが報告されています。
5. すぐできる対策
- スマホの使用時間を意識的に減らす — スクリーンタイム機能やアプリ制限を活用
- 寝る1時間前はスマホを見ない — 紙の本やストレッチに置き換える
- SNSのフォロー整理 — 見るだけで疲れるアカウントはミュートや解除
- スマホ姿勢の改善 — 画面を目の高さにし、こまめに深呼吸
まとめ
スマホは生活を便利にする道具ですが、使い方を誤ると脳や心に大きな負担をかけます。
「使う」ではなく「使わされる」状態になっていないか、一度立ち止まって見直してみましょう。
小さな習慣の変化が、あなたのメンタルを守る大きな一歩になります。
病院勤務・整体の経験から、心と体の健康に役立つ情報を発信しています!
整体のご予約をご希望の方は、以下いずれかのリンクからお気軽にお問い合わせください👇
📷【Instagram】▶︎ @relax5.4
📄【ジモティー掲載ページ】▶︎ 整体メニューや価格はこちらから
✉️【ブログお問い合わせフォーム】▶︎ ご相談・予約はこちらからどうぞ

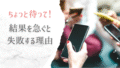
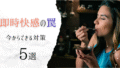
コメント