「怒ると血圧上がるよ!」
という言葉があるように、
怒りや不安を抑え込むと胃腸の働きが停滞したり血圧が上がる反応が起きます。
これは自律神経の中の交感神経による作用になります。
自律神経:交感神経(興奮状態)と副交感神経(リラックス状態)の2つからなります。
つまり、感情は「心の安定」だけでなく、身体の健康を保つ鍵でもあるのです。
感情と身体は“双方向ループ”でつながっている

怒ると心臓がドキドキする。悲しいと胸が苦しくなる。
反対に、深呼吸すると落ち着いたり、胸を張ると前向きな気分になったり。
これは、感情と身体が互いに影響し合うから起こります。
「からだ」が「感情」へ作用する
感情は脳だけでなく、体の状態からも生まれます。
体が反応する → その信号を脳が意味づける → “感情”として感じる という順序です。
- 心拍が上がる、呼吸が浅くなる → 「不安・恐れ」と感じる
- 呼吸が深まる、筋肉がゆるむ → 「安心・安らぎ」と感じる
- 腸の動きが停滞する → 気分が落ち込みやすくなる
「感情」が「からだ」へ作用する
感情が起こると、体内では自動的に自律神経が働きます。
自律神経とは?
心拍・呼吸・消化などを無意識にコントロールする神経で、状況に応じて2つのモードを切り替えています。
- 交感神経:活動モード。緊張・興奮・「戦う/逃げる」ためのスイッチ。
- 副交感神経:休息モード。リラックス・修復・癒しのスイッチ。
この2つがバランスを取ることで、心身の安定が保たれています。
機序: 感情 → 自律神経 → 体の変化
- 怒り・不安 → 交感神経が優位 → 心拍上昇・血圧上昇・筋肉緊張・胃腸が止まる
- 安心・感謝 → 副交感神経が優位 → 呼吸が深まる・消化が促進・免疫が上がる
ホルモンと感情の関連性
感情が動くと、脳からホルモン(体のメッセージ物質)が分泌されます。
- アドレナリン:危険を察知したときに出る。体を「戦うモード」に。
- コルチゾール:ストレスホルモン。長期的な緊張で増えすぎると疲労や不調を招く。
- セロトニン:安心や満足を感じるホルモン。腸で約90%がつくられる。
- オキシトシン:「幸せホルモン」。人とのつながりや安心感で分泌される。
感情⇄身体のループで整える
感情を無理にコントロールしようとすると、体に緊張が残ります。
しかし、体から整えると感情も自然に落ち着く。これが「こころとからだの双方向ループ」を活かす鍵です。
- 深呼吸 → 副交感神経が働く → 安心感が生まれる → 体の力が抜ける
- 怒りや焦り → 交感神経が働く → 呼吸が浅くなる → 不安が増す
つまり、感情と身体は互いにスイッチを押し合っているのです。
【エビデンス】ポジティブな姿勢が回復を早める

感情は一方的に身体に影響するだけでなく、身体の状態や姿勢、表情が感情を形づくるように、感情の持ち方もまた身体の回復に影響します。
ハーバード大学の研究では、「自分の回復に主体的に関わろうとする人」「前向きな感情を持つ人」のほうが、手術後や病気からの回復が早い傾向があると報告されています。これは、ポジティブな感情が副交感神経を活性化させ、免疫機能や組織修復を促すためです(Fredrickson, 2001)。
逆に、ストレスや不安が強いと、身体は「危険から逃げるモード(交感神経優位)」になり、回復に必要なエネルギーが抑えられてしまいます。つまり、感情は単なる気分ではなく、生理的な回復システムのスイッチでもあるのです。
現代は“交感神経優位”に偏りやすい

現代社会では、多くの人が常に交感神経(緊張・戦うモード)で過ごしています。
スマホの通知・仕事のプレッシャー・人間関係のストレスなど、脳が休まる時間がほとんどありません。
交感神経は短時間なら集中力を高めてくれますが、長時間続くと体は常に「危険」と判断し、慢性的な緊張状態になります。
- 呼吸が浅くなる → 酸素不足・疲労感
- 筋肉がこわばる → 肩こり・腰痛・頭痛
- 胃腸が止まる → 便秘・食欲不振・胃もたれ
- 睡眠の質が低下 → 朝スッキリ起きられない
このように、体のスイッチが“休息モード(副交感神経)”に切り替わらないまま、常にアクセルを踏み続けている状態が「現代型ストレス反応」です。
副交感神経を働かせる=“安心”を思い出す

副交感神経が働くとき、体は修復・再生モードに切り替わります。
実はこれは「安心していい」「もう危険じゃない」という体からのサインでもあります。
- 深呼吸する → 脳が「安全」と判断 → 心拍が落ち着く
- ゆっくり話す・微笑む → 表情筋がゆるみ → 副交感神経が働く
- 湯船につかる・陽の光を浴びる → 体温上昇 → 緊張がゆるむ
つまり、副交感神経を整えることは「ただリラックスする」ためではなく、
生命が本来のリズムを取り戻すプロセスでもあるのです。
こころとからだを“分けない”生き方へ
私たちはしばしば「心が疲れた」「体が疲れた」と別々に語りますが、実際には同じ現象の表と裏。 心が落ち着けば体も回復し、体がゆるめば心も穏やかになります。
それが、感情と身体がつくる双方向ループの本質です。
だからこそ、感情を無理に抑えず、体の声を丁寧に聞くこと。
そして、忙しさの中でも少し立ち止まり「安心できる時間」を取り戻すこと。
それが今の時代における、最もシンプルで確かな“心身のケア”です。
参考文献
- Damasio, A. R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Putnam.(感情が身体から生まれる仕組みを神経科学的に説明)
- McCraty, R., & Childre, D. (2010). Coherence: Bridging Personal, Social, and Global Health. Alternative Therapies in Health and Medicine, 16(4), 10–24.(心臓と感情のコヒーレンスについて)
- Kiecolt-Glaser, J. K. et al. (2002). Emotions, Morbidity, and Mortality: New Perspectives from Psychoneuroimmunology. Annual Review of Psychology, 53, 83–107.
- Fredrickson, B. L. (2001). The Role of Positive Emotions in Positive Psychology: The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions. American Psychologist, 56(3), 218–226.(ポジティブ感情が回復を促す理論)
- Crum, A. J., Salovey, P., & Achor, S. (2013). Rethinking Stress: The Role of Mindsets in Determining the Stress Response. Journal of Personality and Social Psychology, 104(4), 716–733.(ストレスへの心の持ち方が生理反応を変える研究)
- Sternberg, E. M. (2001). The Balance Within: The Science Connecting Health and Emotions. W.H. Freeman and Company.
- Thayer, J. F., & Lane, R. D. (2009). Claude Bernard and the heart–brain connection: The neurovisceral integration model of emotion regulation and dysregulation. <em>Journal of Affective Disorders, 112(1–3),</em> 3–13.(副交感神経と情動調整の関係)

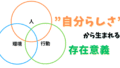

コメント