中世ヨーロッパの健康法と誤解 — 当時の常識と現代の視点から考える
入浴は健康に悪い?中世の意外な常識

中世ヨーロッパでは、入浴はかえって健康を害すると信じられていました。現代の私たちからすると驚きですが、なぜ当時の人々はそう考えたのでしょうか?
その背景には、戦争やペストの流行、宗教的価値観、そして当時の医学的常識が深く関わっています。
当時の健康観と背景 — 宗教と四体液説
中世ヨーロッパはキリスト教が社会の中心にあり、健康や病気の解釈も宗教的でした。病気は神の罰、または悪魔や魔女の仕業とされ、治療よりも祈りや贖罪が重視されることもありました。
医学的には古代ギリシャのヒポクラテスやローマのガレノスが提唱した「四体液説」が受け継がれていました。これは、血液・粘液・黄胆汁・黒胆汁の4つの体液のバランスが崩れると病気になるとする考えです。
また、衛生観念は現代とは大きく異なり、「悪い空気(ミアズマ)」が病気を運ぶと信じられていました。このため、都市部では香を焚いたり、花束を持ち歩くことが流行しました。
中世ヨーロッパの代表的な健康法と誤解

1. 入浴は病気のもと
12〜13世紀ごろまで、ヨーロッパの都市には公共浴場が数多く存在し、庶民から貴族まで利用していました。しかし、14世紀のペスト大流行以降、浴場は「病気の温床」として恐れられるようになります。
浴場の湯を介して感染症が広がると考えられ、さらには不道徳な行為の温床と見なされるようになり、多くが閉鎖されました。その後、人々は香水やリネンの着替えで体を清めるようになります。
2. 放血療法(瀉血)
四体液のうち、血液が過剰と判断されると、体から血を抜く「放血療法」が行われました。ヒルや専用の刃物で血を抜き、バランスを回復させようとしたのです。
軽い症状や一部の病気には効果があった可能性もありますが、多くの場合は体力を奪い、命を縮める結果となりました。
3. 悪い空気(ミアズマ)対策
ペスト流行時には、街中に漂う悪臭が病気の原因と考えられました。医師たちは長い鳥のくちばし型マスクを被り、その中にラベンダーやローズマリーなどのハーブを詰めていました。
この独特な姿は「ペスト医師」として有名で、恐怖と同時に当時の必死な感染対策の象徴ともなっています。
4. 食事療法
食べ物は四体液説に基づき、「温性」「冷性」「湿性」「乾性」に分類されました。体が冷えているときは温性の食べ物(肉、ワイン)を、熱があるときは冷性の食べ物(野菜、果物)を食べるとされました。
これは経験的な栄養学の萌芽ともいえますが、必ずしも科学的根拠があったわけではありません。
5. 占星術と医療
医師の多くは占星術を学んでおり、月や星の位置から手術日や薬の処方日を決めました。星座ごとに支配する体の部位があり、その影響を避ける日程調整が行われたのです。
これは迷信の域を出ませんが、当時は天体の動きと人間の健康が結びついていると信じられていました。
実は一理あったこと

中世の健康法にも現代で評価される部分があります。カモミールやローズマリーなどのハーブは抗炎症や鎮静効果があり、実際に薬効が認められています。
また、ハーブ水やワインで手を洗う習慣は、殺菌効果が一定程度あったと考えられます。食事と健康の関係に注目した点も、栄養学の先駆けといえるでしょう。
現代から見たまとめ
中世の健康法は、迷信や誤解に基づく部分も多かった一方で、当時の社会状況や環境の中では合理的な面もありました。「現代の常識」も数百年後には非常識と呼ばれるかもしれません。
健康知識は時代とともに更新され続けるものです。当時の歴史を知ることで、私たちはより柔軟に自分の健康法を見直すことができます。
今の自分の健康法を見直してみよう
中世の人々も、限られた知識の中で最善を尽くしていました。私たちもまた、情報があふれる現代で、自分に合った方法を選び取る力が求められています。
過去の歴史から学び、自然治癒力を高める生活を心がけること。それこそが、時代を超えて共通する健康の秘訣なのかもしれません。
おすすめ関連記事
▶古代中国の養生思想と東洋医学|自然と調和し心身を整える健康法
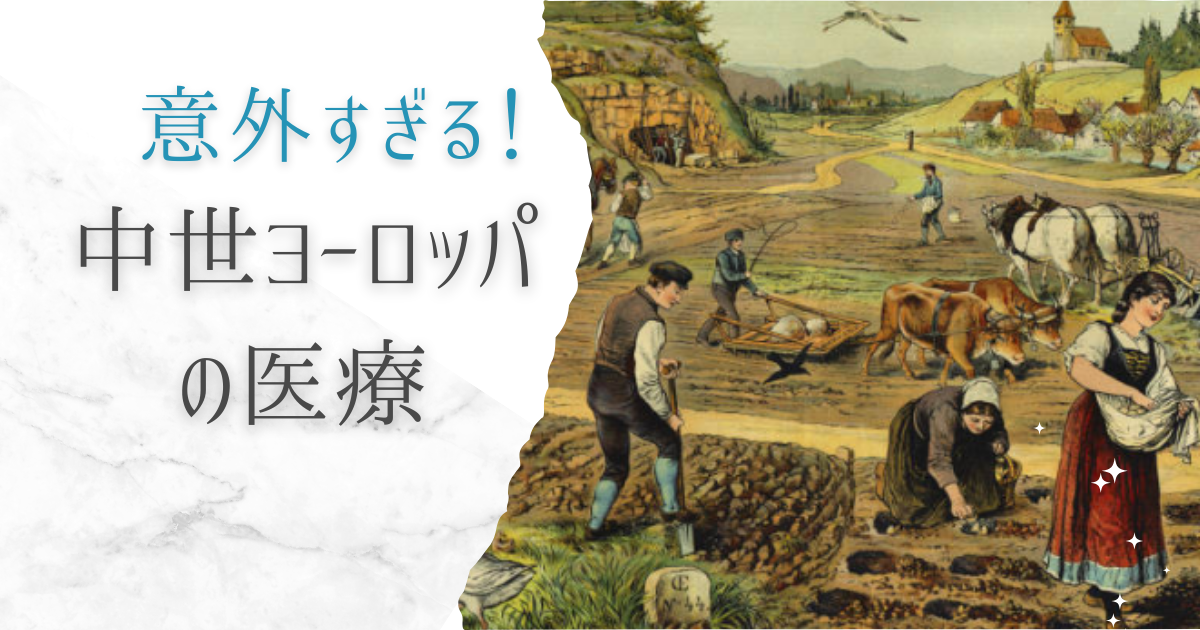

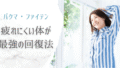
コメント